美味しい病院食・まずい病院食
まずい病院食で3人に1人が栄養失調になる事実
スイスにあるジュネーブ大学病院では、1,700名の入院患者を対象とした病院食の調査が行われました。その結果、3人に1人の入院患者は病院食が理由で入院中に栄養失調になってしまい、そのまま退院していたことがわかりました。栄養失調にいたるまで病院食を食べられなかった、残してしまった原因は以下です。
- 味が美味しくない
- 温かいものが食べたいのに、提供されるときには冷えている
- 食事の選択肢が少なすぎる
- ゆっくり食べられない(配膳から回収まで20分)
- 食欲がわかない
味やメニューのバリエーションについては好みがあるので、工夫を凝らしてもすべての患者さんを満足させるのは難しいかもしれません。ただし、食事を提供する温度や食事にかける時間、食欲のわく盛り付けなどにおいては、まだまだ改善の余地がありそうです。
美味しい病院食=贅沢ではない
病院食は患者さんの健康状態を保つために欠かせないもの。栄養バランスの良い献立が基本となっていますが、どんなに栄養バランスの良い食事も完食されなければ意味がありません。
完食してもらうには、見た目・味・食べやすさを大切にすること。そして患者さんの1人ひとりの味の好みや苦手を知ることが必要です。「美味しく食べられる病院食」は決して贅沢ではなく、健康な身体づくりにおいて必要なものなのです。
病院食の完食を目指すなら、以下のポイントを見直してみましょう。
- 食事内容を選択式にする(和食・洋食、パン・ごはんなど)
- 月に1度のイベント食の導入
- 色どりや見た目を重視する
また、これらの見直しを行ってくれる給食会社に調理を委託するのもひとつの手です。
見た目・味・食べやすさにこだわる!
病院給食を委託できる会社まとめ
病院食にまつわる口コミ評判
病院食を実際に利用している人のリアルな口コミをまとめました。
味に関する声

調味料が染みるはずの煮物ですら味が薄かったです。私は普段から薄味の食事が好きなので、毎日おいしく頂いていましたけどね。普段から濃い味の食事に慣れている人は物足りないかもしれません。

「病院食だしお肉は食べられないだろうな…」と思っていましたが、お肉・お魚どちらも出ました!ただ、残念ながらどちらも薄味でパサパサ…。ご飯はなんとも言えない食感でした。病院食にはふりかけが必須だと思います。

病院食なのでしかたないかもしれませんが、味が薄いですね。私は入院したときに食事や味付けの制限がなかったので、大部屋で先に入院されていた方から調味料をかりていました。

確かに味は薄いですけど、病院食を食べる時間が一番の楽しみです!食事ができるようになるまでは面会の時間が一番楽しみだったのですが、食事ができるようになってからは食べられることのありがたさをひしひしと感じています。

骨折で入院したときに病院食をいただきました。骨折だけで身体は元気なので、味気のない病院食に飽きてましたね。院内にコンビニがあったので、よく通っていました。

はなから病院食に期待なんてしていませんし、美味しさも求めていませんでした。元々そう思っていた私ですらがっかりするくらい、提供された食事は薄味で量が少なかったです。衝撃でした。5分もしないうちにあっという間に食べ終わってしまいます。メニューは普段口にしない酢の物や煮物が多かったですね。3泊4日の入院生活でしたが、食事を日は前日、味が薄くて量が少なかった印象しかありません。

病院食は選択肢が少ないのが残念ですね。私がいた病院は追加料金を支払うと食事をグレードアップできる施設だったので、1,000円払ってグレードアップしてもらったんです。実際に食べてみた感想としては…正直払わなくても良かったかな。グレードアップしたメニューのほうが見た目は良くて美味しそうなんですが、やっぱり味がいまいちでした。
献立のバリエーションに関する声

病院によると思いますが、私が利用したときはご飯・メイン・小鉢2種類のパターンが多かったですね。肉と魚だと、肉の比率が多め。ハンバーグが出るときもあって、思っていたより献立のバリエーションは豊富でした。

1つのおかずがどん!と出される感じではなく、小さな小鉢で何品も出される感じでした。私が普段家で作っている食事よりもおかずの品数が多かったです(笑)。

普段の食事は「ザ・病院食」って感じで質素なのですが、クリスマス・元旦などのイベント時には少しだけ豪華なメニューが出ます。ずっと薄味の病院食だと飽きるので、イベントの食事がちょっとした楽しみです。

3ヶ月ほど入院していました。私が入院した病院は2種類のメニューから選ぶ方式でしたが、どちらも食べたいと思えるメニューではなかったです。献立内容がローテーションだったので変わりばえがなく、入院期間中に食べたいと思えるメニューには出会えませんでした。

短期間の入院の場合は、おそらく決まったメニューだと思います。私は短期入院しか経験をしたことがないので、決まったメニューを食べていました。長期間入院する方は和食と洋食のうち好きなほうを選べるみたいでうらやましかったです。
食事の温度に関する声

食事の提供温度は病院によると思います。私が入院した病院では、温かいものもきちんと提供されていました。味も美味しかったです!退院したあとに自分で作って見ようと思えるようなメニューもありました。食事が美味しかったので、入院生活もちょっとだけ楽しめましたよ。

温かい料理は冷えて、冷えた料理はぬるい状態で提供されました。たくさんの入院患者さんがいて同じ時間帯に配膳されるので、仕方がないのかもしれませんが…残念な気持ちでした。

持病があるので病院によくお世話になっています。病院食は年々クオリティが上がって美味しくなっていて嬉しいです。私がお世話になっている病院は、配膳のお盆に温冷機能がついていて、温かいものと冷たいものが適温で食べられる工夫がされています。
食器や盛り付けに関する声

病院食の味付け・メニュー内容もそうですが、配膳するときに使うお盆や食器の色も工夫してほしい…。病院って感じの色を見ただけでなんだか食欲がなくなります。

入院していたときはミキサー食でした。単体のメニューならまだいいけど、肉じゃがのようにたくさんの素材が入るメニューをミキサーにかけると色が…(苦笑)。栄養バランスや味は変わらないかもしれませんが、いかんせん食欲がわきません。見た目と食感の大切さを身をもって実感しましたね。
デザートに関する声

朝食にはフルーツ・ヨーグル・ゼリーのデザートがついてきました。味気ない食事が多いぶん、デザートがつく朝食は嬉しくてテンション上がりましたね。

デザートはフルーツが多かったです。ぶどう・パイナップル・メロンなど。缶詰はあまり出なかった気がします。予算の問題か、フルーツのほうが栄養価が高いのかわかりませんが、季節や時期を問わずにフルーツ三昧でした。
病院食の導入事例
病院の食事は治療の一環として考えられているため、できる限り完食したいところ。「美味しそう」「食べたい」という思いを掻きたて、食への関心を持たせられる給食が求められます。実際に提供されている病院給食の導入事例を見てみましょう。
医療法人社団北腎会 坂泌尿器科病院


引用元:LEOC公式サイト(https://www.leoc-j.com/voice/?p=373)
「食事が入院中の楽しみになるように」という思いで医療給食を導入している坂泌尿器科病院。導入しているのはLEOCの医療給食です。
理事長はお米の質に対するこだわりが強く、患者食・職員食ともに北海道産ゆめぴりかを採用しています。また、患者さんの食事に対する意欲やわくわく感を高めるため、アンケート内容をもとに月に2回「お楽しみ弁当」を提供。彩りや盛り付けにもこだわっており、患者さんから感謝や喜びの声が多く届いているそうです。
医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター


引用元:LEOC公式サイト(https://www.leoc-j.com/voice/?p=428)
直営給食と院外のセンター給食を経験したのち、新築移転のタイミングで院内に厨房をつくり、委託給食サービスを導入した彩の国東大宮メディカルセンター。月2回の給食改善のため、委託給食会社LEOCと定例会議を実施しているそうです。
株式会社LEOCが提供している病院食は、食事全体をみても彩りが鮮やかで、食器にもこだわっています。「味が薄くて不味そう」という病院給食のマイナスイメージを払拭しています。品数も多いため、思わずどれから食べようか迷ってしまいそうな病院食です。
病院食の種類
病院食といえば「健康のためにカロリー計算してつくられた薄味の食事」というイメージが強いですが、実際には次のようなジャンルに分けられています。
一般食(常食)
一般食とは、病院で出される代表格的な食事です。健康な人が普段食べているような、ごはん・汁物・おかずといった食事を指します。病院食は健康面を重視してつくられるため、素材の旨味を生かした薄味のメニューが多め。患者さんが味気ないと感じたり飽きたりしないよう、調理方法を工夫してヘルシーな揚げ物や肉料理をメニューに盛り込んでいる施設も増えています。
主食は栄養価の高いご飯が主流ですが、最近はパン・うどんを主食に使用している施設も少なくありません。
嚥下力に合わせた食事
病院には、噛む力が低下した患者さんや飲み込む力が衰えている高齢者がたくさんいます。そのため、患者さん嚥下力(食べ物を飲み込む力)に合わせ、柔らかさや形態を工夫した食事を提供する必要があります。嚥下食と呼ばれるやわらかい食事は、噛む力・飲み込む力に合わせて提供できるよう大きく7種類にわけられます。
1.軟食(なんしょく)
軟食にあたるのは、一般食よりも柔らかいご飯やおかゆ。うどんなどの麺類は、食べやすいよう短くカットしたうえで、茹でる時間を長くして柔らかく調理したものが提供されます。軟食は、胃腸が弱っている人や咀嚼がうまくできない人向けのメニューです。そのため繊維が多かったり、歯ごたえがあったり、クセのある食材はあまり使用されません。
2.きざみ食
軟食と同じく、咀嚼(噛んだり飲み込んだり)がうまくできない人向けのメニューです。飲み込む力が弱い人よりも、歯がなくなってうまく食事ができない人向けのメニューとして提供されることが多め。1つの食材を1センチ以下のサイズに刻んで作られるため、咀嚼力が低下している人でもある程度スムーズに飲みこめます。
3.ゼリー食
ゼリー食は、1度作った病院食をミキサーにかけたあと、ゼラチンやでんぷんなどで固めてゼリー化した食事です。献立や味付けは、基本的に一般食・軟食と変わりません。ゼリー状でツルっとしているので、固形物を飲み込むのが苦手な方でも嚥下しやすいでしょう。美味しく食べてもらうため、固さや舌触りなどにこだわってゼリー食をつくっている施設・給食会社が多めです。
4.ミキサー食・ペースト食
病院食をミキサーにかけたのち、誤嚥防止のためにとろみをつけた食事です。ゼリー食よりも形がなくてトロッとしているため、噛んだり飲み込んだりするのが苦手な方でも食べやすいとされています。噛まずに食事ができるので、主に歯がない人や噛み砕く力が低下した人に利用されています。
5.流動食(りゅうどうしょく)
おかゆを炊いた時に出てくる上澄みの重湯、汁物やヨーグルトなどの液体をメインに構成される病院食です。基本的に「ドロッとした液状の食事=流動食」と思われがちですが、茶碗蒸しのように噛まずに食べられる固形物も流動食にあたります。高熱や手術直後で、胃腸が弱っている人でも食事ができるように工夫された食事です。
6.ソフト食
見た目は一般食と変わらないのですが、舌で押しつぶせる柔らかさに仕上げられた病院食です。柔らかくてつるんとした食感の素材を使っているのが特徴。普段ミキサー食やきざみ食を利用している人でも食べられます。「ソフト食の見た目が嫌い。美味しそうに見えない」という声もありますが、最近では揚げ物(例:コロッケ)を再現したソフト食も登場しています。工夫すれば患者さんの食欲を高められるため、参考にしてみるとよいでしょう。
特別治療食
特別治療食とは、身体的機能(例:咀嚼力や嚥下力)を考慮してつくられた食事ではなく、病気によって摂取できる栄養素・カロリーに制限がある人のために提供される食事です。代表的な特別治療食を2種類ご紹介します。
1.糖尿病食
食事をする(糖を摂取する)と血糖値が上昇するため、体内ではインスリン(※1)というホルモンが分泌されます。糖尿病はインスリンの分泌量が少ない、または分泌されたインスリンがうまくはたらかない病気。そのため、普通の人と同じ食事をすると血液中のブドウ糖を処理しきれず、高血糖状態が続き、さまざまな合併症(動脈硬化や感染症、脂質異常症など)が起こります。
糖尿病食は、糖尿病の症状悪化や合併症を防ぐために欠かせない食事です。具体的に糖尿病食とはどんな食事なのかご紹介します。
※1:血液中のブドウ糖を必要なぶんだけ臓器細胞に取り込ませるホルモン
食物繊維の多い食事
食物繊維は根菜に多く含まれている栄養素です。低カロリーでありながら、空腹感を満たしてくれる特徴があります。糖尿病食には食物繊維が多く使われている理由は、栄養素の吸収速度をおだややかにする性質があるため。食物繊維を摂取することで、血糖値の急激な上昇もある程度抑えられます。1日あたりの理想的な摂取量は20〜25gです。食物繊維が多いそば1人前でも含有量は3.7gなので、自炊で毎日20gの食物繊維を担保するのは難しいところ。管理栄養士さんのもと糖尿病食をつくって提供すれば、患者さんにも満足してもらえるでしょう。
肉類の脂が少ない食事
インスリンがうまくはたらかない糖尿病患者は、糖代謝だけでなく脂肪の代謝も低下してしまいます。そのため、脂質の多い食事を続けていると血液中のコレステロールや中性脂肪が増え、「脂質異常症」を合併してしまいます。また、血糖値が高いぶん、糖が血液中のコレステロールが酸化させて動脈硬化になるリスクが高いため、注意が必要です。
糖尿病食では、脂質を摂りすぎを防ぐため、肉類の脂を極力取り除く調理方法が用いられます。例えば煮物や蒸し料理。肉を焼く際はフライパンではなく網を使い、脂を落としてから提供されます。
オメガ3系脂肪酸を使った食事
オメガ3系脂肪酸とは、EPAやDHA(魚に含まれる油)、ALA(くるみや大豆などに含まれる油)の総称です。日本人5万2,680人を対象として行われた研究によれば、魚介類の摂取量が多い男性ほど糖尿病発症のリスクが低かったとのこと。魚介量の摂取量が最も少なかったグループと比べると、糖尿病のリスクが約3割も低かったそうです。研究結果から、オメガ3系脂肪酸にはインスリンの分泌量やはたらきを改善する効果が期待できると考えられています。
また、オメガ3系脂肪酸は血液中の悪玉コレステロール値を上げることなく、中性脂肪値や血圧を下げる働きをもっています。積極的に摂取することで脂質異常症や動脈硬化対策にもつながるため、糖尿病食において重宝されています。
塩分量を減らした食事
糖尿病患者は高血圧を合併するケースが多いため、1日に6mg未満の塩分量を目標とした糖尿病食が提供されます。調味料を使用する際は減塩醤油や減塩みそなどを使用。また、醤油や塩の代わりにレモンやゆずを使って風味をつけるなどの工夫がされています。
2.腎臓病食
腎臓病食は腎不全の進行を遅らせるための食事です。進行がスローになれば、生活の制限が多い「透析療法」への移行を遅らせることができます。具体的に腎臓病食とはどんな食事なのか確認していきましょう。
たんぱく質控え目の食事
腎臓は血液の中から体に必要なものを再吸収し、不要なもの(老廃物や塩分)を尿として体の外へ追してくれる臓器です。たんぱく質を摂取すると体内で必要なぶんだけエネルギーに代謝され、余ったものは老廃物となって排出されます。
腎臓機能が低下している人は、たんぱく質を代謝する際に腎臓に負担がかかってしまうため、大量摂取は禁物です。また、排出しきれなかった老廃物が体内に溜まってしまうと尿毒症になってしまいます。
腎臓病食は腎機能を活性化させないよう、たんぱく質の量が控え目。まったくたんぱく質を摂らない食生活だと体内のたんぱく質が壊されてしまうため、適量のたんぱく質を摂取できる食事が提供されます。
塩分を抑える
腎機能が低下すると、塩分を排泄する機能が低下します。塩分を体外へうまく排出できないため、一般の人と同じ量の塩分を摂取すると、血圧上昇・むくみに繋がるのです。1日の塩分摂取量は3〜6gが理想的。加工食品や練り製品は塩分が多く含まれているので、腎臓病食ではあまり使用されません。
摂食・嚥下の5期
「摂食・嚥下の5期」とは次の5段階のうち、どの段階で食事に妨げが起きているかを確認するものです。
- 先行期(認知期):何をどのように食べるか判断をする
- 準備期(咀嚼期):食べ物を咀嚼して食塊を形成する
- 口腔期:食塊をのどに送りこむ
- 咽頭期:食塊をのどから食道へ送りこむ
- 食道期:食塊を食道から胃へ送りこむ
文面だと難しく見えますが、簡単に説明すると「食事をするときのもぐもぐ、ごっくんを5段階に分けたもの」です。食事を噛んだり飲みんだりするのが難しい患者さんには、段階に合わせた病院食の提供が必要不可欠。摂食・嚥下の段階に合わない食事を提供すると、食べ物が気道に入って窒息したり、肺炎になったり、食事そのものが苦手になってしまう可能性があります。
嚥下食にまつわる体験談
嚥下食を経験した方のリアルな体験談を2つご紹介します。
1.口腔底がんにまつわる嚥下食のエピソード
病院食がまずくて食べられない
普段からホームパーティーを開催するほど食事が大好きだった旦那が口腔底がんになり、口の中を大きく切除する手術を受けました。術後は奥歯1本しか残らなかったため、舌と上あごですり潰せる流動食がメインになりました。幸い味覚は残っていたのですが、食事ができるようになって2日目には病院食を食べてくれなくなりました。不思議に思って、私も病院食を食べてみると…正直おいしくなくて。これを舌と上あごですり潰しながら数時間かけて食べるって考えたとき、食事が嫌になる気持ちもわかりました。
口腔状態に合った流動食が見つからない
退院したときに医師から言われた食事のアドバイスは「嚥下機能に問題がないので、柔らかいものならば、なんでも食べられます」この一言のみ。介護食の市販品にも、当然流動食はあります。しかし食事が好きな旦那の口に合うものはなかなか見つからず…。また、流動食をいろいろ試した結果、軟らかくてもツルツルしたものや口の中に張り付く食材は誤嚥に繋がると学びました。
介護食づくりのストレスが爆発
市販品の流動食を諦め、手探り状態で介護食をつくりはじめました。流動食に欠かせないフードプロッセッサーは、使うのも洗うのも大変。とにかく時間がかかるので、1日ずっとキッチンにこもる日々が続き、ストレスが溜まっていました。そんなとき旦那から「お粥の水分量を変えて欲しい」と言われて大爆発。昨日は食べられたのにそんなわがまま言わないで!って、夫につい強くあたっちゃったんです。小さな食のこだわりに全部応えていたら私がもたないと思って。でも、それは単なるわがままじゃありませんでした。手術の傷が治るにつれて口の中の感覚が変わっている。だから、昨日は食べられたものも今日はうまく食べられないと言っていました。
旦那を「おいしい」と言わせる流動食
「流動食=ミキサー」と言う概念に捉われていたけれど、ドロドロした見た目はどうしても美味しそうに見えません。そこで、旦那が好きだったクリームシチューを嚥下食にすれば食欲がわくかも?と思いついたんです。
野菜は7ミリ角ぐらいに切って、舌でつぶせるやわらかさになるまで煮込みました。お肉の代わりに、やわらかくてジューシーな鮭のハラスをほぐして入れました。完成したシチューを食べた旦那は何度も何度も「おいしい」って言ってくれて、すごくうれしかったです。
シチューのほかにも、つみれ団子を応用してふわふわのトンカツをつくったり、食パンよりもやわらかい麩でフレンチトーストをつくったり、食欲を高められるように色鮮やかな野菜のピュレをつくったり…。旦那に喜んでもらえるのがすごくうれしくて、またおいしいものを食べさせてあげたいという思いが強まりました。
2.誤嚥性肺炎にまつわる嚥下食のエピソード
ペースト食になって2か月で体重10kg減
肺の手術で入院している間に誤嚥性肺炎になりました。退院時に医者から言われたのは「普通の食事では肺炎を繰り返す可能性があるからペースト食に切り替えてください」ということだけ。いつまでこの生活を続ければいいのか、どうすれば普通の食事を食べられるようになるのか説明はありませんでした。
退院してしばらくは妻が見つけてきてくれた市販品のペースト食を食べていました。月10万円くらいかかるのに、見た目はぐちゃぐちゃで味も微妙。どうしても食欲がわかず、体重は2か月で10kgも落ちてしまいました。
食べるリハビリでペースト食を卒業
訪問診療でお世話になっていた先生の話によれば、「食事の機会が減ると筋力が衰えてさらに嚥下力が低下する。このままでは胃ろう(胃に通した管から栄養を送る方法)になるかもしれない」とのこと。そこから伊勢原協同病院の摂食機能療法室の方にも協力いただき、食べるリハビリが始まりました。
私が普通食を禁止されていた理由は、また誤嚥して肺炎になってしまう可能性があったから。そこで、誤嚥しない食事の姿勢や口を閉じて飲み込むコツなどを指導してもらいました。家族は先生たちから軟らかくて食べやすいメニューの調理方法を教えてもらったそうです。
そこから少しずつ食事が苦じゃなくなり、ペースト食以外を食べられるようになっていきました。3か月ほどで家族と同じ普通の食事ができるようになり、身体も元気になりました。
当時、指導されたのは次のような内容です。
- 誤嚥を防ぎ安全に食べられるように食事の姿勢を整える
- テーブルに体を近づけて、肘を乗せる
- 足の裏は床をつくように固定した姿勢で食べる
- 小さいスプーンで口を閉じて咀嚼。飲み込むときも口を閉じて飲み込む
- 底が浅い湯飲みで顎を上げないで飲む
病院食に管理栄養士が欠かせない理由
栄養士と管理栄養士は、どちらも栄養摂取をサポートをするのが主な仕事です。活躍できる就職先や仕事内容など共通している部分が多々あります。大きな違いは「誰を対象に栄養指導をするか?」です。
| 栄養士 | 健康な人に対して、食や栄養のアドバイスをする |
|---|---|
| 管理栄養士 | 健康な人だけでなく、高齢者・傷病者にも食や栄養のアドバイスをする |
つまり、病院食には管理栄養士が欠かせません。管理栄養士は栄養士よりも専門的な知識を持っているため、高齢者・傷病者に対して個別で栄養管理・指導が可能。また、管理栄養士が在籍している病院には次のようなメリットがあります。
- 利用者ごとに嚥下機能の評価が適切にできる
- 1日3回の食事が楽しめるようなメニューを考案してくれる
- 病院所属の場合、医師・看護師とチームを組み、治療のサポートをする
- 個別指導を通じてコミュケーションを取り、食事のサポートをする
栄養士も栄養・食事に関するプロですが、より専門的な部分をカバーしてくれるのが管理栄養士です。病院食は食事療法につながるほか、「食べることの楽しみを伝える」という大切な役割も担っています。
本来食事は楽しいものですが、中にはうまく咀嚼・嚥下ができず食べることがストレスになってしまう方もいるでしょう。管理栄養士は、個別で栄養管理・指導しながらコミュケーションを積極的に取り、利用者がどんな人かチェックしてくれます。食事を苦痛に感じていた患者さんが管理栄養士とのコミュニケーションを通して、「この人がアドバイスしてくれるから頑張りたい」「長生きするためにも病院食を食べよう」といった考えにシフトチェンジするケースも少なくありません。
病院食に関するアンケート調査
医療系情報サイト「Nursing-plaza.com」は1,457名の男女を対象として、病院食に関するアンケートを行いました(※調査期間2014年1月7日~2014年2月5日)。
アンケート結果から、病院食に対するイメージや実際に食べてみたときの声をまとめています。
入院中病院食を食べたことがあるのは約7割!
「入院中に病院食を食べたことがあるか」というアンケートでは、解答者の約7割の人が「食べた経験がある」と回答しました。病院食の経験がある人は男性より女性のほうが多め。これは妊娠・出産のために入院した人が病院食を利用しているからかもしれません。
入院中に食べていた病院食の種類TOP3
| 1位 | 一般食(常食) |
|---|---|
| 2位 | 産後食 |
| 3位 | 軟飯食(5分がゆ、7分がゆなど) |
病院食を利用した人の6割以上が一般食を食べている
入院中に出された病院食の種類をアンケートしたところ、一般食と答えた人が全体の6割を占めていました。手術を受ける人や感染症患者のほか、骨折した人や宿泊を伴う人間ドック利用者なども含まれるため、このような結果となったのでしょう。消化器官や体調に著しく問題がないかぎり、ほとんどの病院では一般食が提供されます。
2番目に多かったのが、出産したあとに出される産後食でした。病院や施設によっては、出産後にお祝い膳を提供しています。和・洋・中の豪華な食事やフランス料理のフルコースなど、バリエーション豊富なメニューを提供している産婦人科もあんだるとか。産後のお祝い膳の内容を見て、出産する施設を決める女性もいるそうです。
3番目に多かったのは軟飯食(おかゆ)です。病院食として食べたことがあると回答した人は全体の6%。短期間の入院時、または手術後の食事として提供されることが多いそうです。
病院食を食べた感想TOP3
| 1位 | 味が薄い |
|---|---|
| 2位 | 栄養バランスが考えられている |
| 3位 | おいしい |
病院食の感想は意外にポジティブ
一般的に病院食は「味が薄くておいしくない」というイメージが強いようです。そんななか「栄養バランスが考えられている」「おいしい」といったポジティブな意見も見られました。主に女性のアンケート回答者の意見だったので、産後食に対して評価している方が多いと思われます。一方男性の場合、肯定的な意見と否定的な意見の割合が同じくらい。味・温度・彩り・量に関する意見は、男女どちらも肯定・否定の割合が同じでした。
食べたことがない人抱く病院食のイメージTOP3
| 1位 | 味が薄い |
|---|---|
| 2位 | 栄養バランスが考えられている |
| 3位 | 内容が質素 |
病院食を食べたことがない人のイメージはマイナス印象が多い
病院食を食べたことがない人を対象にしたアンケート結果から、ほとんどの人が「味が薄い」といったイメージをもっていることがわかりました。他にも「おいしくない」「量が少ない」「冷たい」「見た目が悪い」など、どちらかといえば食べたことがない人のほうがマイナスイメージをもっていることがわかりました。
病院食の改善に求めることTOP3
| 1位 | 味の美味しさ |
|---|---|
| 2位 | メニューの選択制 |
| 3位 | 快適に食べられる環境 |
病院食の改善に求めるのは味とバリエーション
アンケート回答者の5割以上は、美味しさやメニューのバリエーションを改善してほしいと考えているそうです。病院食の「味」は時代と共に変化をしているものの、まだ施設によってバラつきがあります。実際「病院食が美味しくない」と感じる人の割合が多いのも現状です。
メニューは和食・洋食のいずれかを選択できるところが少しずつ増えています。夕食だけが選択制といった条件付きのパターンもあるようです。
食事環境は病室のベッドの上で食べるのが一般的ですが、体調が良い日は気分転換に食堂で食べたいという声もありました。1日中ずっと病室にいるとストレスが溜まってしまうため、院内に食堂や売店を設けておくと良い息抜きの場になるかもしれません。
病院食に関するアンケートに答えた人の声

最近の病院は、病院食も温かくてメニューも利用者の意見を聞いてくれます。病院食が楽しみの1つになっていいと思います。

病室で食べるのではなく食堂など別の場所で食べられるといいなと思いました。ずっと1日中病室にいると息がつまります。食堂があれば気分転換もできそう。

食器にもう少し工夫があるといいなぁと思いました。食材に合わせて彩り豊かなものを使ってくれると嬉しいです。
病院・高齢者施設・
保育園・会社・寮で給食会社の導入を検討している方へ
数多くある給食会社の中から問合せする会社を絞り込むのは大変なことです。
そこで、Googleで「給食会社」と検索した際に上位表示する137社を調査し、病院・老人ホーム・保育園・社食・寮といった幅広い施設の給食に対応していて、公式HPで導入事例を公開している給食会社を紹介(2022年8月30調査時点)。
給食会社に委託したい、新たに乗りかえたいと考えている施設は、自社のこだわりにあった給食会社を探してみましょう。
当サイトでは、参考になる事例が豊富で導入後のイメージが沸きやすい給食会社を“おすすめ”としています。
対応力重視なら…
要望が通らない
給食委託で
もう悩みたくない施設の味方
名阪食品

- 対応力の高さと柔軟性を
評価する事例が豊富 - 施設の要望を叶えるための
工夫や仕組みが充実
味にこだわるなら…
食のエキスパート
による給食で
施設の評判を落とさない
LEOC
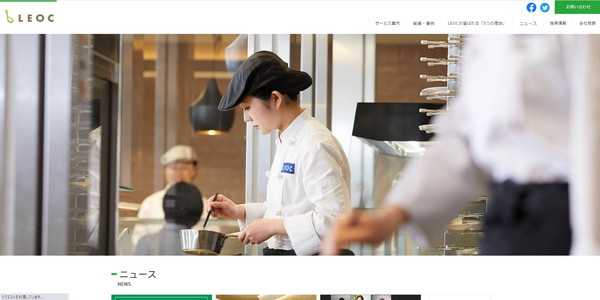
- ミシュラン掲載の外食事業を運営(2019年時点)
- 熟練の料理人が
メニューを開発
安定感を求めるなら…
信頼できる老舗に
業務を任せて
施設運営を円滑に
馬渕商事

- 60年以上の長期経営が
証明する安定感 - 創業当初から給食は
「手作り」というこだわり
大量供給が必要なら…
大量供給や複数拠点への
供給に
苦戦する施設にピッタリ
エームサービス

- グループ全体で
1日約130万食の給食を提供 - アスリートやホテルにも
サービスを展開
給食会社を比較する際、差がつくポイントである「味」「対応力」「コスト」は、実際に問い合わせてからでないとわかりません。
そのため、複数社に問い合わせた後、コンペティションで給食を試食し、導入を検討するのが一般的。まずは給食会社に問い合わせて、給食の味やクオリティをチェックしましょう。


